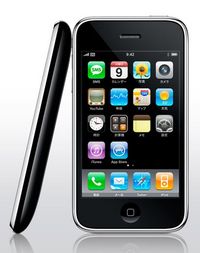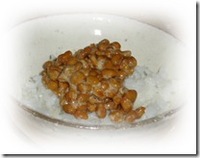2008年05月17日
内視鏡によるがんの粘膜下層切開剥離術を導入

(クリックで記事へ 熊本経済)
社団魁正会 服部胃腸科(熊本市新町2丁目、尾田恭院長)は、内視鏡治療において胃がんなど消化器系がんの新しい切除術である粘膜下層切開剥離(はくり)術(通称ESD)を積極的に導入している。
この粘膜下層切開剥離術は、1回の切除で5㎝から10㎝の大きな病変でも一括切除が可能であり、従来の方法より完全切除率が飛躍的に向上した点が特徴。治療法は、がんの病変を確定し、病変部に色素散布し十分な観察後、切除範囲をマーキングし、切除すべき範囲を決める。そしてITナイフ、フックナイフなど特殊な電気メスを用い、マーキング部のさらに外側を全周切開し、病変の下にある粘膜下層に局注液を注入して病変部を盛り上げ、剥離していく方法。
従来は、がん組織の根元にワイヤーをかけ、高周波電流により焼き切る内視鏡的粘膜切除術法(EMR)が一般的だったが、この方法では2㎝を超えるがんの場合、数回に分けて切り取る「分割切除」となり、病変を一括して切除することが難しいため、切り取った組織の病理学的評価が難しく、取り残しによる居残発生の危険性が指摘されていた。内視鏡下の切除術は、患者にとっては開腹手術に比べ、肉体的、精神的負担が大幅に軽減され、術後の生活の質の向上が期待される。06年4月から胃がんの治療に保険適応され、現在では食道、下部消化管へと応用範囲が拡大している。
同院では「従来の方法に比べ、切開剥離術は治療時間が長く、出血や穿孔(せんこう)といった合併症の頻度が高いことも事実であり、医師の熟練度がポイントとなります。当然、症例数の多い医療機関を選別することも大切な要素です」と話している。 (甲木)
医学の進歩も、日々著しいですね。
私の母も、急性白血病で他界しましたが、その約6年前と今では生存率も延命率も格段に向上しているそうです。
もちろん死なない人間はいませんが、病での不意の死は本人にとっても回りにとっても悲しいことです。
再三述べていますが・・・医療研究にも、もっと予算をつけてほしいものです。
先進国と比べても最低レベルの研究予算では、現場の研究者の方にあまりにもひどい仕打ちです。
Posted by セレスピード熊本 at 09:57│Comments(0)
│【政治・経済】
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。