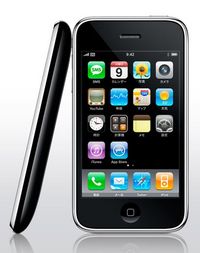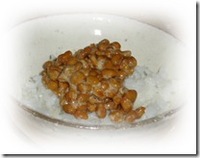2008年05月18日
高度不妊治療助成

(記事をクリックで記事へ・熊日コム)
県と熊本市が2004(平成16)年度から始めた高度不妊治療への公的助成制度の利用者が増えている。07年度は計785組が利用。初年度より3.7倍増えた。昨年度から、利用回数など内容が拡充されたことが増加の理由。ただそれでもなお「経済的負担が大きい」という声や、治療できる医療機関が少ないという問題もある。利用者からは「さらに充実してほしい」という声も出ている。
不妊症とは、妊娠を希望している夫婦が通常の性生活を行っているにもかかわらず、二年を経過しても妊娠しない場合をいう。
不妊治療では、排卵誘発剤など薬物治療については健康保険が適用されるが、体外受精や顕微授精といった高度不妊治療には健康保険は適用されず、一回当たり三十万円から五十万円の費用がかかる。
県や同市の助成制度は、国の補助事業で、国が二分の一、県(熊本市の場合は同市)が二分の一ずつ負担する。夫婦の所得合計が七百三十万円未満を対象に、一回当たり十万円まで年二回、通算五年間受けることができる。
利用件数は初年度が県市合わせ二百十一組、〇五年度二百七十一組、〇六年度三百五十五組と年々増加。〇七年度からは、回数が年一回から二回に拡大、所得制限も六百五十万円未満から七百三十万円未満に緩和されるなど制度が拡充したため、前年度より二・二倍増えた。
助成を利用して体外受精した宇土市のパート女性(38)は「二回利用し、合計二十万円の助成があったので、非常に助かった」と評価。ただ、それでも治療費全体の半分以上は自己負担したという。八代市の会社員女性(35)も「助成を受けて体外受精をしたが、それでもやはり経済的負担は大きかった」と話す。
経済的負担の軽減以外にも問題は残されている。助成を受けるには県や熊本市が指定する医療機関での治療が条件だが、県内の指定医療機関は計八カ所。熊本市と八代市にあるだけで、うち六カ所は熊本市にある。このため遠方から通院する患者も多いが、「厚生労働省の施設基準や一定以上の不妊治療の技術も求められるので、今のところ指定病院を急速に増やすのは難しい」(県)という。
県内の産婦人科医らでつくる熊本生殖医療研究会(代表・片岡明生片岡レディスクリニック理事長)は「全国では一万八千人の赤ちゃんが、体外受精以上の高度な不妊治療で生まれており、特別な治療ではなくなりつつある。指定医療機関の拡充を含め、さらに利用者が使いやすい制度に見直していくべきだ」と話している。(田端美華)
Posted by セレスピード熊本 at 16:32│Comments(0)
│【政治・経済】
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。