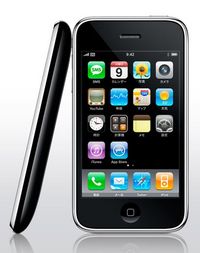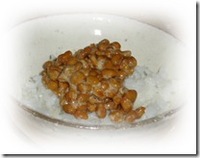2008年05月30日
魂は生まれ変わる?
5月29日23時41分配信 読売新聞
読売新聞社が17、18日に実施した年間連続調査「日本人」で、何かの宗教を信じている人は26%にとどまり、信じていない人が72%に上ることがわかった。
ただ、宗派などを特定しない幅広い意識としての宗教心について聞いたところ、「日本人は宗教心が薄い」と思う人が45%、薄いとは思わない人が49%と見方が大きく割れた。また、先祖を敬う気持ちを持っている人は94%に達し、「自然の中に人間の力を超えた何かを感じることがある」という人も56%と多数を占めた。
多くの日本人は、特定の宗派からは距離を置くものの、人知を超えた何ものかに対する敬虔(けいけん)さを大切に考える傾向が強いようだ。
調査は「宗教観」をテーマに面接方式で実施した。
死んだ人の魂については「生まれ変わる」が30%で最も多く「別の世界に行く」24%、「消滅する」18%--がこれに続いた。

よく海外に行くと、あなたの宗教はなんですか?という質問を多く聞きます。
終戦以来、日本は良くも悪くも宗教の自由をGHQにより制定させられました。
日本は神の国だから、戦争に負けるはずないというような科学や物理を無視した、
当時の指導者による暴挙で何百万人ものかけがえのない人が死に、
その結果、日本人にとって宗教は信じるに値しない物になってしまったのかもしれません。
しかし、同時に2万以上の宗教法人が乱立する世界に類をみない国になってしまいました。
私は、仏教徒ですが本来仏教(釈尊が残された経)が果たしてきた役割と、
現在の日本の仏教とはかけ離れていると思っています。
信徒(檀徒)が減るのも当たり前です。
私たちの次の世代の頃には、信仰の対象としてではなく、観光地としての神社・仏閣しか残らないのではないでしょうか?
終戦以来、日本は良くも悪くも宗教の自由をGHQにより制定させられました。
日本は神の国だから、戦争に負けるはずないというような科学や物理を無視した、
当時の指導者による暴挙で何百万人ものかけがえのない人が死に、
その結果、日本人にとって宗教は信じるに値しない物になってしまったのかもしれません。
しかし、同時に2万以上の宗教法人が乱立する世界に類をみない国になってしまいました。
私は、仏教徒ですが本来仏教(釈尊が残された経)が果たしてきた役割と、
現在の日本の仏教とはかけ離れていると思っています。
信徒(檀徒)が減るのも当たり前です。
私たちの次の世代の頃には、信仰の対象としてではなく、観光地としての神社・仏閣しか残らないのではないでしょうか?
Posted by セレスピード熊本 at 13:43│Comments(4)
│【政治・経済】
この記事へのコメント
たぶんそうなってしまうのでしょうね!
うちはもう神棚は祀ってませんね
正月もご先祖様の仏壇に手を合わせるだけです
うちはもう神棚は祀ってませんね
正月もご先祖様の仏壇に手を合わせるだけです
Posted by zeppe at 2008年05月30日 14:06
こんにちわ☆
大学院時代にスリランカの客員教授の1年間お世話係でしたので、仏教美術の事を学ばせて頂く機会がありました。
スリランカは仏教国で、日本も一応は仏教徒の多い国だと思うのですがぜんぜん違う印象です。(全部英会話だったので、誤解等も混じってるかもですが、、、)それは、シルクロードとかの影響うんぬんだけでなく
スリランカのそれは生きてる仏教というか。。。。
>>私は、仏教徒ですが・・・
行司さんの意見に賛同です。
宗教の果たす役割って、形式だけなんだろーか??と考えさせられたのを思い出しました~
しえー長くてすいません
大学院時代にスリランカの客員教授の1年間お世話係でしたので、仏教美術の事を学ばせて頂く機会がありました。
スリランカは仏教国で、日本も一応は仏教徒の多い国だと思うのですがぜんぜん違う印象です。(全部英会話だったので、誤解等も混じってるかもですが、、、)それは、シルクロードとかの影響うんぬんだけでなく
スリランカのそれは生きてる仏教というか。。。。
>>私は、仏教徒ですが・・・
行司さんの意見に賛同です。
宗教の果たす役割って、形式だけなんだろーか??と考えさせられたのを思い出しました~
しえー長くてすいません
Posted by プライマリー at 2008年05月30日 19:00
at 2008年05月30日 19:00
 at 2008年05月30日 19:00
at 2008年05月30日 19:00zeppe様
あと10年もすれば、特定の宗教を信じている方は、激減するのではないでしょうか?
親が宗教に対し無関心なのに、子供が信仰心をもつはずがありません。
あと10年もすれば、特定の宗教を信じている方は、激減するのではないでしょうか?
親が宗教に対し無関心なのに、子供が信仰心をもつはずがありません。
Posted by 行司 at 2008年05月30日 21:20
at 2008年05月30日 21:20
 at 2008年05月30日 21:20
at 2008年05月30日 21:20プライマリー様
全然長くて結構ですよ!
このテーマは、人生の一代問題ですから!
古くから日本で仏教は祭りごとと結びつき、戸籍や地域学校の役割を果たしてきました。
私の個人的意見ですが、日本仏教が衰退したのは、明治維新の妻帯の許可だとおもっています。
聖職者が家庭を持つと子供が生まれ、その子の為に、蓄財や家督を残そうとします。
当たり前ですが、出家とはそういうしがらみを捨てる行為だったはずです。
そこには、法(仏法)の広布という目的は生まれにくくなり、世俗的な世襲に固執しまう。
在家と変わりません。
そこら辺が、私は違うと思うのです。
明治以前の僧侶は、基本的には妻帯は認められていなかったはずです。
そこには、純粋に仏教を伝授していく精神が在ったはずです。
全然長くて結構ですよ!
このテーマは、人生の一代問題ですから!
古くから日本で仏教は祭りごとと結びつき、戸籍や地域学校の役割を果たしてきました。
私の個人的意見ですが、日本仏教が衰退したのは、明治維新の妻帯の許可だとおもっています。
聖職者が家庭を持つと子供が生まれ、その子の為に、蓄財や家督を残そうとします。
当たり前ですが、出家とはそういうしがらみを捨てる行為だったはずです。
そこには、法(仏法)の広布という目的は生まれにくくなり、世俗的な世襲に固執しまう。
在家と変わりません。
そこら辺が、私は違うと思うのです。
明治以前の僧侶は、基本的には妻帯は認められていなかったはずです。
そこには、純粋に仏教を伝授していく精神が在ったはずです。
Posted by 行司 at 2008年05月30日 21:31
at 2008年05月30日 21:31
 at 2008年05月30日 21:31
at 2008年05月30日 21:31※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。