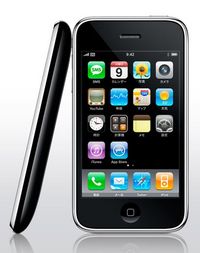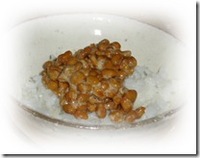2008年06月01日
なぜ日本の農業は?
先週は、これからの世界経済の変動によって、食料を輸入に頼るこれまでの日本経済のあり方は大変危険であることを説明しました。欧州諸国が1970年代の米国による大豆の禁輸をきっかけに食料自給率を高めたのに比べて、60年代に6割だった日本の食料自給率は、今では4割を切るところまで低下しました。
日本に農地が足りないためではありません。度重なる減反政策や耕作放棄や裏作の停止で、日本の作付延べ面積は、ピークであった1960年代の半分にまで落ちました。
しかも、このままでは、日本の農業は衰退することが確実です。担い手となる農家の高齢化がさらに進み、後継者が激減するからです。掛け声ばかり食料安全保障や自給率向上を訴えても、流れを変える現実の政策はいまだに実行されていません。
高度成長時代の成功体験が衰退の元凶
なぜ、日本の農業は衰退を続けるのでしょうか。農業を衰退させてきたのは、政治だけではありません。農家の選択、消費者の行動、つまり、日本人全体が、農業の衰退に関与しているのです。
でも、戦後の農業は、高度成長の時代までは非常にうまくいきました。ところが、その成功体験に引きずられ、新しい現実に適応することを怠っているうちに衰退が始まり、いまだに方向を変えることができないのです。
こうした点において、農業問題は道路問題と実によく似ています。農業と道路、国土の根幹を成すこの2つが、21世紀の現実に応じて変わるべき時が来たのです。
それでは、どこから変えるべきなのでしょうか。そんな問題意識から、2004年に「『平成の農地改革』で田園からの産業革命を」という論文を中央公論(2004年3月号)に書きました。食料問題が注目を浴びる今、皆さんと一緒に日本が農業大国、食料大国に生まれ変わる道を考えてみたいと思います。
農業大国の可能性を秘めた日本
まず、比較論から入りましょう。どうして欧州諸国は日本よりも食料自給率が高い国や、食料の輸出量が輸入量を上回る食料輸出国が多くあるのでしょうか。日本が条件に恵まれないためではありません。
土壌と水に恵まれ気候の変化に富む日本は、寒冷でやせた土壌のドイツや英国、雨が少ないスペインやイタリア南部よりも恵まれているはずです。大雪が降る新潟や秋田でこそ、雪解け水と夏の暑さのおかげで、本来熱帯の植物である米がおいしく作られるところに、恵まれた風土と日本人の努力の歴史とが現れています。
欧州の穀物の中心である小麦が、連作が利かず農地当たりの収穫量が限られる作物であるのに対して、日本の米は、連作どころか、1年のうちで二期作や二毛作も可能な優れた作物です。
日本の農産物の品質が欧州に劣るためでもありません。それどころか、各地の名産牛や豚や鶏、芸術品のように美しくておいしい果物や野菜、世界一おいしいと讃えられるお米など、世界に冠たるグルメ国家らしく、日本の農産物の品質の素晴らしさは、日本を知る外国人には常識です。
それなのに、なぜ日本でなく欧州が、農業大国となったのでしょうか。
農村が経済の成長拠点となった欧州
まず、欧州諸国は、自国の農業を伸ばすために大きなコストをかけています。EU(欧州連合)の予算の過半は、農家への大幅な補助金です。
食糧生産の増加だけでなく、環境保護のためにも、農家への補助金が使われています。ドイツやスイスやフランスの美しい田園風景は、農家への直接の補助金で守られていると言っていいでしょう。
しかし、それ以上に大きいのは、欧州では、農業を中心とした田園産業と言うべき産業が幅広く発達し、経済の根幹をなすようになったことです。