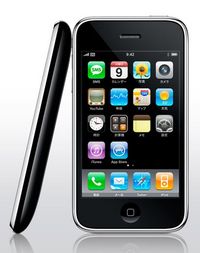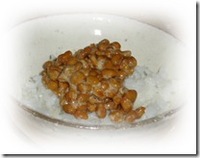2008年06月06日
セアカゴケグモ

公園駐車場で大量の毒グモ「セアカゴケグモ」 愛知
2008年6月5日(木)19:28
国土交通省中部地方整備局は5日、愛知県愛西市立田町の国営木曽三川公園「東海広場」の駐車場で、外来種の毒グモ「セアカゴケグモ」が大量に見つかったと発表した。推計で約600匹いたとみられるが、バーナーで焼いて駆除した。整備局は「かまれると、吐き気やめまいといった症状が出る。見つけても素手で触らないで」と注意を呼び掛けている。
整備局によると、5月21日に利用者から通報があり、専門家が確認した。主に駐車場の排水路に生息しており、24~30日に駆除した。どのような経路で侵入したのかは分かっていない。この場所ではすべて駆除したと考えられるが、整備局は5日から近くの木曽川、長良川、揖斐川の河川敷でほかに生息していないかどうか、約5キロ間隔で生息調査を始めた。
セアカゴケグモ(Latrodectus hasseltii)は、有毒の小型のクモの一種。和名は、「背中の赤い後家蜘蛛」の意味。本来日本国内には生息していなかったが、1995年に大阪で発見されて以降、その他いくつかの地域でも見つかった外来種である。
毒
毒は獲物を咬んだときに、獲物の体に注入されるもので、神経毒である。しかし、性格はおとなしく、手で直接触ったりしなければ咬まれることはない。また、その毒性も死に至る例は非常に少ない。オーストラリアでは古くから代表的な毒グモとして知られており抗血清も存在する。日本でもセアカゴケグモの発生した地域の医療機関で抗血清を準備しているところもある。咬まれた部位は、ちくっとした痛み、あるいは激しい痛みを感じる。その後、咬まれた場所が腫れ、全身症状(痛み、発汗、発熱など)が現れる。手当てが遅れると毒素の効果により皮膚が腐っていくことがあるため、咬まれたら、特に子供は、医療機関での早急な診察が必要である。可能であれば、この毒グモであると判断するために個体を小瓶などに捕獲して医療機関に持参するといいだろう。
Posted by セレスピード熊本 at 17:42│Comments(0)
│【政治・経済】
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。