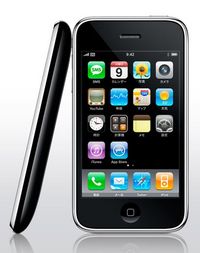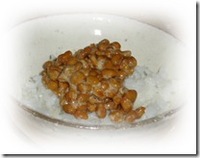2008年07月09日
漁業危機

<漁業危機>/上 安い魚価に燃油高
2008年7月8日(火)13:00漁業を取り巻く危機的な状況を知ってもらおうと、全国漁業協同組合連合会(全漁連)など17団体は15日に一斉休漁する。かつて世界一の「水産王国」といわれた日本の漁業界がいま、どうなっているのか。2回に分けて報告する。【小島正美】
◇「漁師35年で一番苦しい」
「漁師になって35年になるが、今が一番苦しい」。太平洋をのぞむ千葉県の九十九里沿岸で漁業を営む伊藤重一さん(52)=旭市三川=は日焼けした顔に悲壮感を漂わせる。
小型の5トン船に乗り、シラスやヒラメ、タイなどを刺し網などで取る。今月2日夕、漁から帰った伊藤さんは「きょうはシラスの漁獲はゼロだった。ぐるぐる走って、魚群を探そうにも、高い油代が気になって、船を積極的に走らす攻めの漁ができない」と嘆く。
■1年で2倍
小型船は燃油として軽油を使う。価格は1リットルあたり約125円。1年で約2倍にはね上がった。1回の漁で最低でも5000円以上の油代がかかる。1隻5000万円以上もする漁船の償却費の返済も含めると、1日10万円近い水揚げが必要だが、最近は2万~3万円も珍しくない。
魚の浜値(生産者の出荷価格)が安いのも悩みの種だ。かつてはヒラメの浜値は1キロ1万円以上したが、いまは高くて1600円程度。「魚価低迷の中で油代が上がるので、どうしようもない」と肩を落とす。
1970年代にもオイルショックがあり、燃料は高騰した。当時は同じたんぱく源である牛肉など肉類の値段が高く、高騰分を魚価に転嫁できた。だが、いまは肉類が安いため、魚の値段が上がると消費者が肉類に向かい、魚価が上がらない構図になった。
燃油の高騰はあらゆる漁業を直撃している。全漁連の試算によると、漁業生産コストに占める燃油の平均割合は3~4割にもなる。特に大型船で近海に出漁するカツオ一本釣りやイカ釣り漁業は燃油代が4割も占めるため、出漁しても赤字になるだけという。
大型船が使う燃油のA重油が、いまの1キロリットルあたり約11万5000円から13万円に上がると、「漁業経営体の3割前後が廃業に追い込まれる」と全漁連は危機感を募らせる。
A重油が13万円になると、漁獲生産量は現在より約3~5割も減ると全漁連は試算する。そうなると、魚を運んだり、加工したりする加工・流通産業が崩壊するだけでなく、結局は魚の値段が上がり、消費者の家計に響くことになる。
■自給率4割減
危機の背景には、日本の漁業の足腰が弱くなっていることもある。
70年代まで日本の魚介類の自給率は100%を保っていた。最盛期の84年には1282万トンの漁獲量があり、世界1位だった。ところが、排他的経済水域(沿岸から200カイリ)の設定など世界的な公海規制に加え、輸入品の増加で遠洋・沖合漁業が衰退。漁獲量は574万トン(06年)まで下がり、自給率も60%程度に落ちた。
最盛期の漁業生産金額は年間約3兆円(1982年)だったが、いまは約1兆6000億円(06年)と半減。大手スーパーのイオングループ1社の年間売上額は約5兆円。その3分の1しかない。
漁業者の数は過去10年間で約28万人から約20万人に減った。半分が60歳以上だ。
■海外で消費増
国内生産がだめでも輸入に頼ればいいという意見もあるかもしれない。だが、水産庁によると、過去20年間で魚の消費量は日本で減る一方、EU(欧州連合)や米国は2~3割増加し、中国は3倍にも増えた。健康志向から世界中の国が魚を食べ始めたのだ。水産庁企画課の大橋貴則課長補佐は「日本が魚で買い負ける時代に入った」と話す。
例えば、かまぼこの原料となるスケトウダラでも、「国際的な落札合戦で日本は中国やEUに買い負けし、原料の確保が難しくなりつつある」(全国蒲鉾(かまぼこ)水産加工業協同組合連合会)という。
■一斉休漁
全漁連などが一斉休漁を決めたのは、こういう危機的な状況を知ってもらうためだ。東京に約3000人の漁業関係者が集結する。1日だけの休漁のため、市場への影響はなさそうだ。
千葉の九十九里で小型漁船を操る遠藤勝信さん(35)も一斉休漁に参加する。「このままだと魚を取る漁師がいなくなる」と深刻な様子だ。
「若い漁業者が廃業したら、再生は二度と無理」。そんな危機意識を抱く長屋信博・全漁連参事は、実現可能かどうかはともかく、「1匹100円の魚に2円の支援金を上乗せして、スーパーで売ってもらい、その支援金を漁業支援に回してもらうことはできないものか」とスーパーと消費者に支援を求める苦渋のアイデアまで披露する。